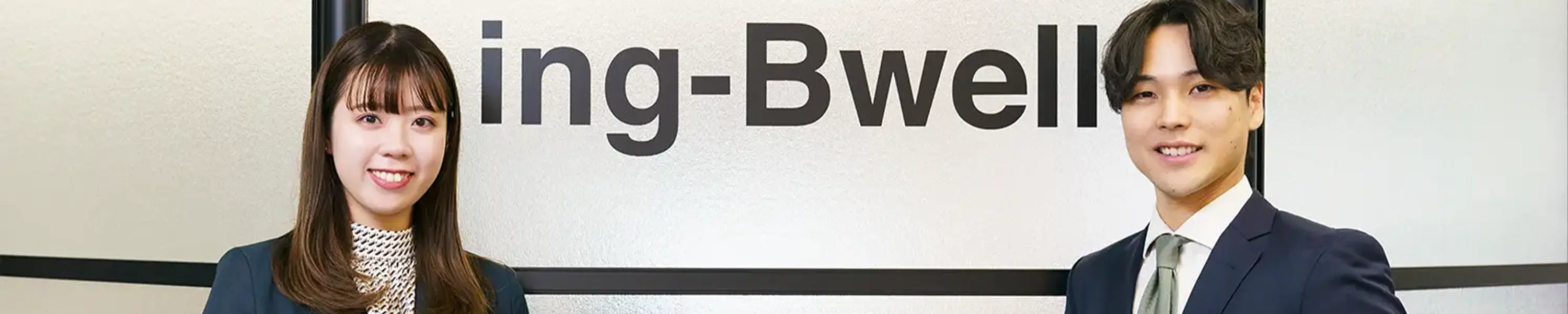採用成功を増やしたい。
その一心で取り組んだ研究から、
笑顔の連鎖をつくりたい。

営業活動以外の取り組みとして、ing-Bwellが大切にしている「研究」。時間を割いて研究できる環境を整備し、研究費用の予算も確保しています。研究を通じて実現したい大きなゴールは、人材採用に力を入れているお客様の採用成功。研究チーム毎にテーマを決めて、深く考え、調べ、答えを導き出していきます。この取り組みからグループ全社を動かすまでになった1つの研究チームにスポットを当て、研究秘話に迫ります。
プロフィール

細川未久
- 入社
- 新卒/2022年4月入社
- 出身
- 福岡県出身
- 仕事で大切にしていること
- 「本当の課題は何なのか?その会社の人事部になった気持ちで考える」
福澤高也
- 入社
- 新卒/2019年4月入社
- 出身
- 神奈川県出身
- 仕事で大切にしていること
- 「悩みや課題をお客様の立場を想像して考える」
お客様の採用成功が、研究活動の源泉。

2019年新卒入社の福澤高也。後輩の2022年新卒入社の細川未久。2人が初めて取り組んだ研究テーマは「Indeedの振り返り観点の明確化」だったという。

「私たちing-Bwellは、グループ会社内で先駆けてIndeedの求人掲載に向けた営業活動を推進していました。基本的にはどの求人メディアも、求人を掲載すると効果レポートという形で、求人のPV数や応募件数をデータとして見ることができます。しかし、Indeedは私たちがこれまでに取り扱ってきた掲載型の求人メディアではなく、運用型の求人メディアということもあり、数値の見え方が変わりました。求職者に何回求人が表示されて、その求人を何回クリックしてもらえて、そこから何件応募につながったか。さらに、クリック率や応募率、クリック単価といった、これまでにない細かな数値が見られるようになったのです。そのため、Indeedで見える数値をどう受け止め、理解し、お客様にお伝えすべきか、という観点を養うことが、私たちの研究テーマになりました。」
お客様と効果の実感を共有できるように、振り返りの観点の追求に没頭した研究当初。そこから研究は次なるステージへと進んでいく。
「僕たちが振り返りの観点を明確にしたことによって、営業の各メンバーの振り返りレベルは上がりました。しかし、数値では測れない課題も浮き彫りになってきたのです。Indeedの応募効果の数値的には合格ライン。でも、応募者の質は不合格ラインといったことが起き、数値の改善以外のところで打ち手はないか、と考えるようになったのです。そこでフォーカスしたのが、求職者の内面。社内の雰囲気や人間関係、仕事のやりがいなどで、自分に合う・合わないを判断する求職者と、人材を募集する企業とのマッチング精度を高めていきたい。これが僕たちの新たな研究テーマになりました。」

小さな会議室で始まった研究から全社プロジェクトへ。

週に1回、福澤と細川が調べてきたことを持ち寄り、議論する研究活動。その場で話を聞いている代表の新野が自らの知見を掛け合わせ、どの方向性に歩みを進めるか、道を示していく。その中で、求職者と企業の相性を高めるために「BIG5理論」という心理学を取り入れてはどうかと、話が進んでいったという。
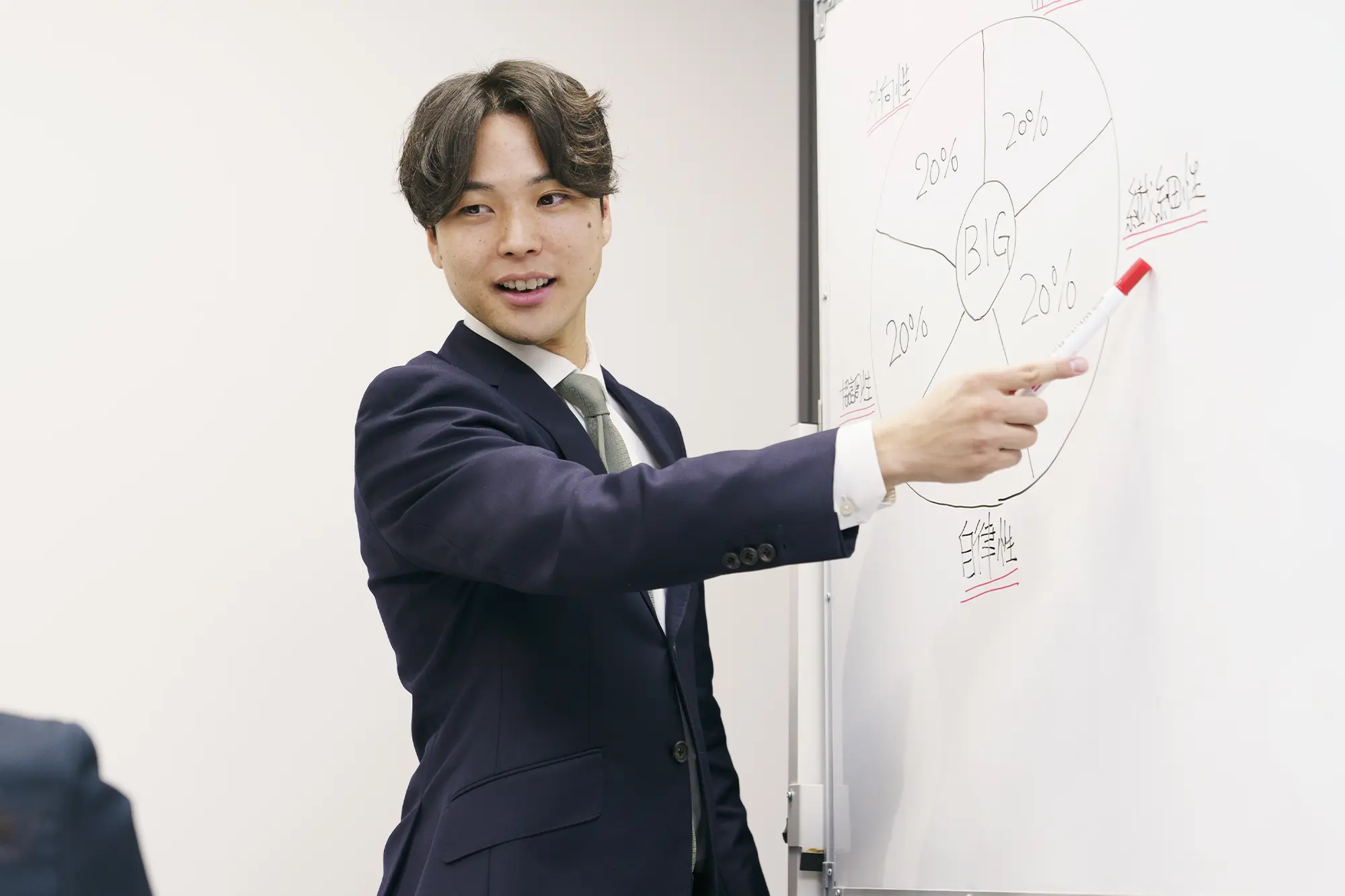
「BIG5理論を用いた採用の仕組みをつくるために、グループ会社に協力を求め、必要なデータを集めていきました。外向的な求職者が好む言葉、内向的な求職者が大切にしている言葉。その他にも、現実的と創造的、直感的と計画的など、求職者を5つのタイプに分け、さらに各タイプごとに好むキーワード(言葉)を5つ選定し、求職者の傾向を25パターンに細分化。そのデータをもとに、社内の雰囲気、人間関係、仕事のやりがいなど、スキルだけではマッチングできない、求職者の内面から採用成功へとつなげていく“マインドマッチ”というサービスの開発に乗り出しました。議論を重ね、マインドマッチが形になりかけた頃、代表の新野がグループ会社が持つ技術との連携を閃いたのです。この閃きがきっかけになって、“マインドマッチ”は一気に全社プロジェクトへと拡大していきました。」
“振り返りの観点がわかると便利だね”という他愛ない会話から始まった研究は、たった1年半で大きな変貌を遂げる。グループ会社の1社に“KIBI理論”という、人の気持ちのちょっとした変化=機微を察する力(機微力)の提唱、研究、サービス開発を行っている会社の技術が加わったのだ。
「“KIBI理論”は、東京大学・千葉工業大学・東京工科大学と共同研究し、海外の学会でも発表、評価されています。さらに独自のアルゴリズムによる感情認識AI技術を組み合わせた“感情AI”も開発していたことから、この2つを掛け合わせた、より精度の高いマインドマッチの開発が進んでいったのです。そして、生成AIによる求人広告の原稿作成機能も実装した“KIBIDANGO”という名称のシステムが完成し、BtoBのサービスとして発表まで漕ぎ着けることができました。ここに来るまで研究をスタートして1年半ですから、物凄いスピード感で物事が進んでいったことに、当事者でありながらも驚いています。」

研究を通じて得られたものは、課題を捉えて解決する力。

小さな会議室での会話からスタートした研究は、今や全社をあげて、数億円規模の開発費を投入するほどの大きなプロジェクトとなった。ここに至るまでに営業活動だけでは得られなかった経験をしてきた2人。どんな成長を実感しているのだろうか。

「営業として日々仕事をする中で、直面する課題がたくさんあります。その課題を解決するサービスやツール、システムが世の中にあって、それを利用する側の人間として素敵なサービスだなと思うことは多々ありました。そんな自分が研究から生まれたアイデアで、新たなサービスの形をつくる。その経験をして、考え方が大きく変わりました。だって、世の中にあるサービスはすべて、0→1(ゼロイチ)ができる特別な人だけがつくれると思っていましたから。自分が感じている課題、誰もが同じように思っている問題を起点に、解決につながるサービスをつくり上げる。こんな貴重な経験ができたことは、自分にとって大きな財産になっています。」
考え方が変わるほどの経験をした福澤。彼と一緒に歩んできた細川はどう感じているのだろうか。
「当時はIndeedを深く理解できていないこともあって、売りにくいという課題を常に感じていました。そこで振り返りの観点を研究テーマに置いたのです。それが結果的に良かったと思っています。振り返りの観点を明確にすることで、Indeedの商品としての未来を感じることができました。どこに課題があり、どうすれば解決できるのか。この課題を捉える力が研究を通じて養われたことで、視野が広がり、お客様への提案力が上がり、Indeedの個人売上が伸びていったんです。営業だけしていたら得られなかった視点、考え方を学べて、お客様の採用成功に結びつけられている。こういう成長体験をさせてくれる社長、チャレンジを応援する会社の文化に感謝しています。」

お客様の実現したい未来を実現できる人材に成長してほしい。その想いを大切にし、社員教育に力を入れているing-Bwell。営業としてのスキルを高めながら、社会で通用するビジネスパーソンの育成に、これからより一層の情熱を注いでいくという。
そして、ing-Bwellの快進撃は始まったばかり。KIBIDANGOを全国に広め、人材採用に苦戦している地方の採用を盛り上げていく準備は着々と進んでいる。東京にいながら、各地の採用に困っている企業様を支援し、日本中に笑顔の連鎖をつくっていく。“採用成功”という大きな目的を掲げ、走り続けるing-Bwellの革新的チャレンジに、ワクワクが止まらない。